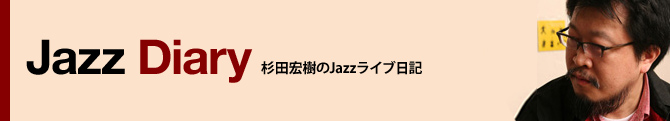« 2009年12月 | メイン | 2010年02月 »
大ヴェテラン・ピアニストの底力を堪能
2010年01月06日
シダー・ウォルトン@丸の内コットンクラブ。シダーは昨年6月の「100ゴールドフィンガーズ」で観ているが、今夜はレギュラー・トリオによるステージということで、最新のシダーを体感できるだろうと期待した。会場は正月気分もあるのか、集客も良好だ。シダーは80?90年代にスウィート・ベイジル・トリオ等の冠トリオでも活躍したピアニスト。親日家で日本のレコード会社からの作品も多数ということで、新たな発見があるとは期待せずに臨んだ。しかしこれは大きな誤解だった。レギュラー・トリオの立役者はウイリー・ジョーンズIIIだった。例えばオープニング・ナンバーの「ウィザウト・ア・ソング」。ブラッシュとスティックを交換しながら、多彩なテクニックを見せる。それは基本的なものなのだが、リムショットを効果的に交えたプレイに、ジョーンズの高いスキルを感じた。シダーはかつてビリー・ヒギンズ(ds)という至宝を得て、自己のトリオを安定させた。今夜ジョーンズに呼応するステージに接して、シダーの揺ぎ無い世界を認識したのだ。作曲家としても優れた実績を残しているシダーは、スティーヴィー・ワンダー「アナザー・スター」で自作曲を想起させるアレンジを披露。他の楽曲を含めて、シダーらしさを随所で感じた。ヴェテランの底力を認識したステージだった。
新年異例のクラブ・ライヴ
2010年01月09日
複数のプロジェクトを同時並行で精力的に展開させているピアニスト/作曲家の藤井郷子。4タイトルの新作を同時にリリースし、その4バンドが一挙に出演するライヴが、新宿ピットインで開催された。通常の同店では昼の部と夜の部に分かれているのだが、今日は午後4時スタートで、休憩をはさみながら4バンドが連続的に演奏する、異例のスタイルだ。トップ・バッターは新作『シロ』を引っ提げたガトー・リブレで、藤井がアコーディオンに専念するカルテット。アルバムのキャッチ・コピーに「美しくも哀しい曲、楽しくも切ない曲」とある通り、藤井の素朴でメロディアスで静の部分を中心としたサウンドだ。2組目はドラム入りカルテットのファースト・ミーティング。新作『カット・ザ・ロープ』のレコーディング・メンバーに加えて、米国から特別ゲストのネルス・クラインを迎えたツイン・ギター編成だ。クラインは独自の小道具やアタッチメントを使用してノイジーなサウンドを生み出し、ケリー・チュルコ(g)との相乗効果を生んだのが収穫。3組目のma-doは通常のトランペット+ピアノ・トリオのカルテットだが、藤井によれば共演者を決めたらこの編成になったとのこと。第2弾となる『デザート・シップ』は昨年の欧州ツアー中に、ポーランドで吹き込んだ新作だ。編成はオーソドックスでも、生まれる音楽は藤井を始めとするこのメンバー独自のものである。トリを務めたのは新作『ザコパネ』をリリースした藤井郷子オーケストラ東京。大編成だから当然、アンサンブルの決め事があるわけだが、それにしてもバンドの空気感が自由だ。そのことがセオリーにとらわれないエネルギーを生む原動力に繋がっているのだと思う。トロンボーンを江戸の火消しパフォーマンスに見立てるなど、笑いを誘う個人技も盛り込んで観客を楽しませた。超満員となった場内の雰囲気がこのイヴェントに対する関心の高さを表した。ミュージシャンにとっても大きな手ごたえがあったに違いない。演奏だけで4時間超のマラソン・コンサートに達成感を共有した。
腕利きギタリストが再来日
2010年01月14日
1970年代以降ジャズ、フュージョン、ブラック関係のスタジオ・ワークで実力を発揮したジョン・トロペイ。個人的には初めて観たジャズ/フュージョンのコンサートだったデオダート74年来日公演の、バンド・ギタリストがトロペイだったことで、特別な縁を感じている。今夜は2007年リリースの最新作『トロペイ10』のレコーディング・メンバーからなる5人編成のバンドが、「ブルーノート東京」に出演した。同作にはキーボード奏者も参加していたが、今回のバンドはオルガン専任のクリス・パルメーロを起用。トロペイがおそらくNYで行うクラブ・ライヴをそのまま日本に持ち込んだような感覚が伝わってきて、かちっとしていないステージの雰囲気は、BNTへの出演を重ねてきたリラクゼーションの反映だとも思った。ブルース・ブラザーズ・バンドでも活躍するルー・マリーニ(sax)とトロペイのやり取りにも共感。いつも裏方に徹するアンソニー・ジャクソン(b)は、やはり仕事きっちりだ。クリント・デ・ギャノンのバック&ソロ・プレイは、スティーヴ・ガッドから多大な影響を受けたもので、今夜は微笑ましさすら感じさせた。アンコールではスティーヴィ・ワンダーの名曲「アイ・ウィッシュ」を披露。いい意味でのマイペースを貫くヴェテラン・ギタリストの今を堪能した夜だった。
実力派歌手が初の本格公演
2010年01月16日
今年でアルバム・デビューから四半世紀となるヴォーカリストのカーメン・ランディ。80年代にCBSソニーが原盤制作をしたことで日本でも知られるようになり、90年代には著名ミュージシャン多数参加のリーダー作が国内発売されて、初期キャリアの頂を形成した。しかしその後のアルバムは日本で出たり出なかったり。黒人女性ヴォーカル界ではいつしかダイアン・リーヴスとカサンドラ・ウイルソンが2トップの座に君臨して、カーメンの椅子は失われた感が強かった。これまでに数度、バンド参加の形で来日した経験があるカーメンが、今回初めて自身のバンドを率い、新作リリースのタイミングに合わせて丸の内「コットンクラブ」に出演。同作『ソラメンテ』はヴォーカルばかりでなく各種楽器もカーメン本人が演奏した完全自作ということで、新たな評価を得た。今回のステージはバンドを配したもので、当然のことながらヴォーカリスト=カーメンの自由度を確保したセッティングだ。「イン・ア・センティメンタル・ムード」「柳よ泣いておくれ」「エヴリタイム・ウイ・セイ・グッドバイ」をアクセントに、家族に捧げたオリジナル曲や歌唱の技巧を駆使したナンバーなど、このアンダーレイテッドなシンガーの魅力と実力を広く伝えられる場面が多数連続した。満員の観客がカーメンのパフォーマンスに共感を寄せたことも特記しておきたい。

難波のトップ・シンガー、本年の助走ライヴ
2010年01月19日
近年は東京で定期的なクラブ出演を重ねて、本拠地の大阪からエリアを拡大しているヴォーカリスト清水ひろみを観た。今夜は初出演となる神保町「アディロンダックカフェ」でのライヴ。同店はこれまで生演奏の実績があり、音響面でのシステムも完備されている。縦長の店内はファンと常連さんで超満員に。ぼくがこれまで共演ステージを観たことのあるピアニスト井上ゆかりとのデュオ。清水にとってこの編成は今夜が初めてだとのことだ。清水は今回、自身のキャリア・アップを図るべく、東京に1週間滞在してクラブ・ライヴを重ねた。出演会場の事情に合わせたブッキングということを踏まえれば、今夜ぼくはこれまでに知らなかった清水の魅力を体感した。立錐の余地がない店内状況は日本のジャズ・ヴォーカル界で何が求められているのかも、だった。3月には再びドン・フリードマンを招いたツアーとレコーディングが予定されている。そのキック・オフとしても成功の一夜であった。
ノルウェーの民族音楽が東京に上陸
2010年01月20日
スカイディ@南青山「月見ル君想フ」。ノルウェーの先住民族サーメ人の伝統音楽ヨイクを現代に継承する歌手インガ・ユーソと、同国で最もアクティヴな新世代ベーシスト=スタイナー・ラクネスが、10年間にわたって活動を続けているデュオ・チームだ。ところが本番直前になってラクネスの個人的事情により、来日ができない緊急事態に。そこで代役としてヨン・バルケ、ビョルン・クラケッグ等のアルバムに参加しているパーカッション奏者ハラール・スクレルーが、ユーソのパートナーを務めることになった。アルバム等で事前にスカイディの音楽を聴いていたわけではない。だからここは真っ白な状態で演奏に向き合う気持ちで臨んだ。ヴェテラン歌手と見受けられるインガは、単に伝統を守るだけでなく、他のジャンルとのコラボにも積極的に取り組む柔軟な考えの持ち主。スクレルーとの共演歴は不明だが、今回のような状況にも動じない姿勢で対応したあたりに、音楽家としての懐の深さを感じた。途中、今夜のセカンド・アクトとして出演したマイア・バルーがフルートでジョイント。マイアのワールドワイドな音楽性とスキルを浮き彫りにすることになった。ノルウェーのヴォーカリストの音作りにも通じる繊細な音楽性を表現したオープニング・アクトのミキ_サカタ(プサルタ、ピアニカ)も特筆したい。
米国の若手注目株、初の単独来日公演
2010年01月21日
昨年6月の「100ゴールド・フィンガーズ」出演で若手実力者の印象を与え、その後初リーダー作『トゥー・シェイド』で、現代を生きるピアノ・トリオとしての気概を示したジェラルド・クレイトン。クレイトン=ハミルトン・ジャズ・オーケストラのコ・リーダーにしてダイアナ・クラールのレギュラー・メンバーでもあるジョン・クレイトン(b)を父に持つサラブレッドだ。今夜はレコーディング・メンバーでもあるトリオを率いて、丸の内「Cotton Club」に登場した。ステージのセッティングは通常とは異なり、ピアノが右側。オスカー・ピーターソンやテテ・モントリューと同じということは、ベースとドラムスの音を聴くバランスの位置関係なのかもしれない。今夜のクレイトンは最新作に基づきながらも、収録曲のお披露目にとどまらない自己主張を展開した。何より「アロング・ケイム・ベティ」「マック・ザ・ナイフ」「いつか王子様が」のスタンダード3曲はアルバム未収録曲。それらはクレイトン初体験の来場者に訴求したことはもちろん、ウォッチャーにはミュージシャンとしての高い意識を伝える格好となった。ステージ中盤にはマーク・ターナー曲を含むオリジナル・メドレーで構成し、斬新なトリオ・コンセプトを浮き彫りに。バッキングとソロの両面で卓越したスキルを披露したドラムスのジャスティン・ブラウンが大収穫。今後経験を積む中で、間違いなくその名を高めるに違いない。
日比谷公会堂開設80周年記念事業
2010年01月23日
第10回「ジャズ・デイ」記念コンサートを日比谷公会堂で観た。午後1:30から7:30までの長丁場ということで、今回は後半を鑑賞。客席に着いた時、ステージに出演していたのが羽根田ユキコ&Trio the Tripだった。予備知識なしで羽根田の歌唱を聴く。現在はファド・シンガーだという羽根田は、なかなかの歌唱力で魅了した。何故ジャズ・フェスティヴァルに参加したのかは定かでない。しかし羽根田は初体験のぼくをも魅了するほどの実力者であった。帰宅後にチェックすると、80年代にポップス・シンガーとしてデビューし、90年代にデヴィッド・フォスターら豪華プロデューサー&ミュージシャンの参加作を吹き込んだ実績の持ち主だと判明。また老舗飲食店を経営するセレブな生き方を知って、ウォッチする気持ちが高揚した。戦後の日本ジャズ界を牽引したドラマー=ジョージ川口の実息である川口雷二は、父親と同じ楽器で2世ジャズマンの道を歩んできた。岡野等+市川秀男+水橋孝を率いるニュー・ビッグ4では、すでに実力では親父を超えた姿を印象付けた。ステージのトリを飾ったのは、10周年記念のために編成されたジャパン・ジャズ・オールスターズ。30年前からイメージが変わらない北村英治は、ベニー・グッドマン所縁のナンバーを取り上げて、80歳とは思えない若々しいプレイで楽しませてくれた。同じ意味で原田イサム(1931年生まれ)の力強いドラムスにも驚嘆。ヴェテランの底力を体感させられたイヴェントであった。
日曜午後のリリース・パーティ
2010年01月24日
ジャズから出発して、R&Bやクラブ方面にもファン層を拡大している邦人女性ヴォーカリストakikoは、昨年12月にノルウェーのブッゲ・ヴェッセルトフトとコラボレートしたデュオ作『ワーズ』をリリースした。これはakikoが所属するレーベルつながりで実現したプロジェクトだったようだが、彼女が以前から北欧のニュー・ジャズを好んで聴いていたのは、意外な印象もある。今日は同作の関連として企画された、akiko選曲によるノルウェ?・ジャズのコンピレーション盤『Sounds ? designed in Norway』のリリース・パーティー@渋谷JZ Bratに出席した。ノルウェー・サーモンを使ったビュッフェ&フリー・ドリンクの会は、まったりとした雰囲気で進行。会場から1時間ほど経ったところで、akiko&ブッゲのパフォーマンスが始まった。途中、レコーディングでオスロに滞在した時の写真がスライドで映写され、フェスティヴァルに出演したステージも含めて初めて訪れた同国に対するakikoの愛情が伝わってきた。これまでのファンには戸惑う向きがあるかもしれないが、北欧ジャズのウォッチャーからすると、よくぞ新しい分野を開拓してくれたと拍手を送りたい気分なのだ。会場でふるまわれたトスカーナ産欧州限定販売の「ECMワイン」が、すこぶる美味だったことも特筆しておきたい。

日本で育つ黒人女性ヴォーカリスト
2010年01月25日
昨年末『イエスタデイ&イエスタデイズ』をリリースしたティファニー。日本のレコード会社からデビューし、順調にレコーディングを重ねて新作で4枚目を数える。今夜は再登場となる丸の内「Cotton Club」でのステージを観た。レコーディング・メンバーを含むカルテットと共に、ティファニーは1曲目から登場。スタンダード・ナンバーの数々を軽妙なMCを交えながら歌う。日本語も堪能なようなので、ステージ・マナーが観客に親近感を抱かせるのが持ち味だ。以前観た時に比べると、歌唱力は着実にアップしていた。前回のパフォーマンスでは疑問符がついたレイモンド・マクモーリン(ts)の技術向上も認められたのも収穫。新作のタイトル・ナンバーはビートルズ・ナンバーとスタンダードを組み合わせた収録曲に由来しており、ジャズ・ヴォーカル好きならばアン・バートンの74年日本制作盤が出典であることに気づくはず。時代を超えて甦った秀逸なアイデアが、ステージでも披露された。ライヴ・シーンでライト・ユーザーにもわかりやすく訴求するティファニーが、自分のポジションを獲得している姿を認識した夜だった
日欧デュオのツアー最終日
2010年01月26日
一昨日のリリース・パーティーでも楽しんだakiko&ブッゲ・ヴェッセルトフトを、「ビルボードライブ東京」で観た。名古屋と大阪公演を経ての東京最終日。akikoは『Words』のレコーディング滞在時にノルウェーのフェスティヴァルにも出演しており、今夜はこのデュオの集大成を期待した。ジャズ?ブラックを守備範囲として、クラブ・ミュージック愛好者からの支持を得ているakikoは自分でも解説したように、今回のプロジェクトではまったく新しい分野にチャレンジ。椅子に座りながらの歌唱は、小型鍵盤や電気機器もコントロールして、ブッゲとの親和的サウンドを醸成する。ブッゲはアコースティックとエレクトリックを巧みにコントロールする得意のライヴ音作りを披露。akikoがステージから退いたコーナーでは、「オール・ブルース」をモチーフにしたソロ・パフォーマンスが、このジャンルのパイオニアならではの技を実感させてくれた。かなりの本気度で新プロジェクトに取り組んだakikoが、この成果を今後どのように発展させていくのかにも注視したい。
新世代のプエトリカンが丸の内に初登場
2010年01月29日
ダヴィッド・サンチェス@丸の内「Cotton Club」。今回が同クラブへの初出演となる。中南米出身で北米に進出したジャズ・ミュージシャンは最近始まった話ではないが、近年のNYシーンでは特に勢いを増している印象を抱く。米国生活が20年を超えたサンチェスは、そのトップ・グループの一角を占めるテナー奏者だ。カルテットを率いたステージは、オリジナル曲を中心とするプログラム。聴き進めるにしたがって、音楽と真摯に取り組むサンチェスの姿勢が浮き彫りになったステージは、同じ黒人ニューヨーカーのマーク・ターナーやブライアン・ブレイドの音楽性とも重なるシリアスなキャラクターが認められた。日本制作のリーダー作もリリースしているノルウェー出身のギタリスト=ラージュ・ルンド(サンチェスのメンバー紹介では「ラーゲ・ルンド」)が、派手さとは無縁のプレイで堅実なスキルを披露。アンコールでマル・ウォルドロン作曲の「ソウル・アイズ」を演奏し、サンチェスがモダン・ジャズの伝統に立脚するジャズマンとしての基盤を伝えてくれたのも収穫となった。
3年ぶりのツアー
2010年01月30日
女優として、同年代では他の追従を許さない実績を積み重ねている松たか子。断続的に行っている音楽活動はすでに10年以上のキャリアがあり、近年はシンガー・ソングライターの才能を開花させている。小田和正主演の年末恒例TBS番組「クリスマスの約束」は、たかちゃんの歌手活動を知らしめる役割を果たし、ファンの間には有難いという感謝の気持ちが広がって、新規小田ファンを生むという興味深い現象も現れた。今夜は3年ぶりとなるツアーの東京公演を「中野サンプラザ」で観た。満員の会場を見渡すと、男女比は7:3だろうか。女性では若いおひとりさまや、40代とおぼしき4人組も認められ、たかちゃんの幅広いファン層を証明した。オープニングはピアノを弾きながら歌うナンバーで、キーボードを含めて今回のステージはシンガーのみならず、鍵盤奏者としての魅力をアピールするコンセプトだと明らかに。最新作『Time for music』の収録曲を中心とした前半に続き、後半は代表曲を並べた選曲で観客は総立ち。アンコールではこの日のために用意することを自らに課したというアップテンポの新曲を聴かせてくれた。せりふたっぷりの3時間舞台を日常的にこなしているたかちゃんにとって、休憩なし2時間のコンサートはさして苦ではないのだろう。余裕あるステージ上のたかちゃんを観ながら、そんなことを思った。開演前に「ハウ・スウィート・イット・イズ」、終演後に「ユア・スマイリング・フェイス」が流れたのは、たかちゃんがジェームス・テイラーのファンだからだろうか。キャロル・キング曲をレパートリーにしているので、可能性は十分ある。会場では「空耳アワー」での共演がきっかけで制作を依頼したという、イラストレーター安斎肇作のキャラクター「まつたけこ」使用のグッズを販売。サンプラザの階段に設置されたオブジェを記念撮影した。

ショールームでのソロ・コンサート
2010年01月31日
西山瞳はトリオを主軸に、様々な編成/共演者とのライヴ活動を意欲的に展開している個性的なピアニストだ。今日はぼくにとって初めてとなる西山のソロ・コンサートを観た。会場は田町のFazioliショールーム。エンリコ・ピエラヌンツィを始め、数多くの著名アーティストが贔屓にするピアノ・メーカーだ。同社が誇る最大サイズのピアノを管理しているため、その名器を使用するファン垂涎のコンサートが企画されたわけである。開演が午後2:00ということで、昼下がりのサロン・コンサートの趣もあった。ピアノ・サウンドの美しさを観客に味わってもらう、との趣旨は、会場に集った全員が1曲目からすぐに共有できた。年間120本のライヴを観ているぼくでも、マイク無しでピアノを聴くチャンスは数えるほど。その意味でこれはかなり贅沢なセッティングだと肌で感じた。今世紀に入って若手人材がさらに豊富になっている邦人女性ピアニスト界にあって、西山瞳は他に類例を見ない独自の個性を輝かせている。最良の楽器を得たステージは満を持したパフォーマンスで、クラブ出演も熱心にチェックする常連ファン以外の来場者にも訴求力大だった。「スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モスト」や「ムーン・リヴァー」のような歌物スタンダードを、予定調和ではなくアレンジする手法とセンスに西山の魅力を再発見。ピエラヌンツィ曲「ドント・フォーゲット・ザ・ポエト」は、メジャー・デビュー前から巨匠を徹底研究した成果と、ステージ・アップした現在が重なり、感慨深く聴いた。今後の定期シリーズを希望したい。終演後にハービー・ハンコックのサイン付きの名器を撮影。