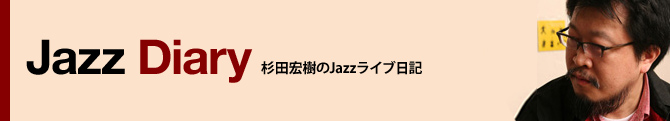« 2010年04月 | メイン | 2010年06月 »
旅する音楽
2010年05月05日
パリを拠点に活動するサックス奏者=仲野麻紀が帰国公演を下北沢「レディ・ジェーン」で行った。仲野さんとは数年前に知り合って以来、連絡を取り合う関係だ。今夜はパリ生まれのギタリスト=ヤン・ピタールとのレギュラー・バンドKyのステージを観た。ゲストに池長一美(ds)が加わったトリオでの演奏。仲野はヴォーカルにも積極的に取り組み、独自に追求する作曲と即興の世界を堪能した。秋には再び帰国するとのことなので、今から楽しみにしている。
ギター・デュオのレコ発ライヴ
2010年05月11日
『シーズンズ』をリリースしたザ・デュオのライヴを代官山「晴れたら空に豆をまいて」で観た。鬼怒無月と鈴木大介とのギター・デュオ・チーム。それぞれが様々な活動をしているギタリストが、スタンダード・ナンバーを中心とした聴きやすい音楽を作るコンセプトは、ジャズ以外の音楽ファンへもアピールする要素が大。ジャズ公演が少ないこの会場を選んだことも含めて、静かなチャレンジ精神を感じ取ったイヴェントだった。
デンマークの若手ピアニストが再来日
2010年05月15日
マグナス・ヨルト・トリオ@新宿ピットイン。昨年の初来日公演がアルバム『サムデイ』に結実し、話題を呼んだ20代のピアニストが再来日を果たした。まず驚いたのは集客。70席超のこの名店をフルハウスにすることは容易ではないが、それを実現させていたのだ。ステージは「エヴリシング・アイ・ラヴ」「パノニカ」「アイ・ミーン・ユー」「タイム・リメンバード」「ジャイアント・ステップス」等の名曲をカヴァーした。アーマッド・ジャマルから影響を受けたと告白した上で演奏した自作曲「ボールルーム・ステップス」が、ジャマルの代表曲「ポインシアナ」を想起させる曲調だったことも特記したい。
春恒例の海外取材に出発
2010年05月20日
西ノルウェーで開催されるJazz Norway in a Nutshellは、世界各国のフェスティヴァル・マネジャー、ジャーナリスト、写真家らの関係者を招くイヴェント。5月下旬の3日間、ぼくは3年連続でベルゲンから招待を受けた。するとしばらくして、ドイツのメールス・フェスティヴァルから5日間の招待メールが届いた。それがタイミングのいいことに、わずか1日をはさんだだけで、メールス?ベルゲンが連続するスケジュールなのである。こちらの事情を伝えると、ドイツ側がフライト・スケジュールを調整してくれた。この間、先方と何度かメールのやり取りをしたのだが、非常に対応が親切で、出発前から期待が高まるばかりだった。往路が午前11:00台出発なのは、いつもの通り。成田からパリまでの11時間20分は、半分の時間を仕事に充てたので、さほど苦ではなかった。初めてのトランジットとなったシャルルドゴール空港は、かなり広く、次の便の搭乗口まで距離がある。そこからさらにバスで移動し、タラップを上って客室に入った。デュッセルドルフまでは1時間半。空港ロビーでシャトル・リムジンのドライヴァーと無事に合流し、21:00前にチェックインした。パソコンのインターネットを確認した後、小腹が空いたので1Fレストランに行く。するとバー・コーナーでメールスのチーフ・スタッフであるReiner Michalke氏と関係者を発見。彼らに合流して、しばしジャズ&ワイン談義で夜は更けていった。
メールス・フェスティヴァル開幕
2010年05月21日
ホテルから会場までは車で15分の距離。関係者向けに無料で用意された送迎車が、随時我々を輸送してくれる仕組みだ。ぼくがこれまでに取材した海外のジャズ・フェスはすべて、ホテルから会場までが徒歩圏内だった。その意味で、今回は初めてのケースである。会場は森林公園の中に巨大テントを設営したもので、近くには露天が並び、来場客はキャンピング・エリアにテントを張って参加する夏フェス・スタイルだ。オープニングを務めたのはテリエ・リピダル&ベルゲン・ビッグ・バンド。先頃ちょうど1年前にベルゲンのNattjazzでお披露目公演を行った時のライヴ盤がECMからリリースされたばかりで、今回は母国ノルウェーの外に出た初めてのステージとなった。まずリピダルと、演奏しながらのパレ・ミッケルボルグが登場。その曲が何と「だったん人の踊り」とは、意表を突かれた。去年とは違う幕開けだ。その後メンバーが入場し、組曲を展開。ステージ後方のスクリーンには、演奏シーンがディレイ処理されて映写される。ストーレ・ストーロッケンがオペレートする映画から拝借したようなセリフを随所に挿入し、それが場面転換の合図となる構成が効果的。ミッケルボルグとリピダルのやり取りは、70年代のマイルス・デイヴィス・グループにおけるレジー・ルーカス&ピート・コージーを連想させる。実際の話、ミッケルボルグは80年代にマイルスと共演しているわけで、マイルスの遺伝子がこのような形で現在に花開いているのだと、感慨もひとしお。最後は引用セリフの「アレサ・フランクリン」で終了した。
続いて登場したのはドンキー・モンキー。フレンチ・ピアニスト=エヴ・リセールと日本人ドラマー大島祐子のデュオ・ユニットだ。2人は「東京JAZZ 2008」のプレ・イヴェントで丸ビルに出演している。デュオとして決してポピュラーではない編成で、独特の世界を表現した。ロック・バンド出身で、パリに移住してから現代音楽と即興演奏を学んだというだけあって、オーソドックスなジャズ・ドラムとは異なるスキルが全開。ヴォーカル曲でも様々なジャンルの経験を滲ませた。3組目はNYで結成されたユニット。2006年メールス・フェス出演者の黒人女性マンタナ・ロバーツ(as,cl)と、昨年のメールスで観客を驚かせたというコリン・ステットソン(bs,as)がフロントのトリオだ。ステットソンが常に音を出し続ける全力疾走プレイで、なるほどこれならインパクトを与えたのも当然だなと納得。激しいフリー・スタイルの一方で、メロディアスな場面もあり、緩急をつけた流れは飽きさせなかった。
メールス・フェスティヴァル2日目
2010年05月22日
午前は今回の招待関係者10名のためのイヴェントに参加。コールマン・ホーキンス&バド・パウエル盤でジャズ・ファンには知られるエッセンへ。世界文化遺産のZeche Zollvereinをガイド付きで見学する。炭鉱業で栄えたこの都市を象徴する広大な工場跡地で、現在は観光スポットになっている。また毎年この時期だけに行われるイヴェント“Shaft Signs”はエッセン・エリアで350個の黄色い風船を上空に飛ばす“インスタレーション”で、タイミングのいい目撃者となった。その後Schlosstheaterへ移動し、ローズガーデンなどを見学。
15:00からメイン・ステージがスタート。トップ・バッターはNYからやってきたSuper Seaweed Sex Scandal。2サックスを含む6人編成は、全員がまだ20代前半の若さ。ロック、パンク、ノイズ、インプロを取り入れたサウンドは粗削りでいて、統制がとれている。注目すべきは紅一点のアルトサックス吉田野乃子。北海道出身で単身NYに渡ってジョン・ゾーンに教えを乞うたスタイルは師譲りで、切れ味のいい高速プレイが存在感を光らせた。メンバー紹介も務めていたので、彼女が実質的なリーダーなのかもしれない。2組目はオランダ、フランス、ベルギー人の混成ユニットの“Network Of Stoppages”。Sanne Van Hek率いる6人編成。昨年のメールスFに出演し、主催者から高い評価を得て、今年はメールス市の“インプロヴァイザー・イン・レジデンス”に選出された女性トランペッターだ。丸1年間、同市に関わることとなったSanneは、フェス委嘱のプロジェクトを準備し、ステージに臨んだ。トランペットをラップトップで加工し、出力。Sanneが吹いていない時でもトランペット音が出る方法で、サウンドを作る。全体的な構造はミニマルに進行し、繊細な音作りといった印象だった。
20:00スタートの夜の部は、スティーヴ・リーマン・オクテットから。5管+vib+b+dsは白人6名+黒人2名。人種と音楽性を直接結びつけるのは不適切かもしれないが、この人選がリーマンの作曲スタイルと、それを有効に実現させるためと無関係ではないはずだ。バンドのキー・メンバーがドラムスのタイション・ソーリーであることは、1曲目が終わらないうちに明らかになった。現在のNYシーンで先端的なジャズに関わっているこの新世代黒人は、いわゆる“ブライアン・ブレイド以降”の技術革新系新感覚ドラマーの一群に属す実力派と言える。フロントのホーンズが知性を感じさせるアンサンブルを生み、ビートの要をパワフルで手数の多いソーリーが担う図式。そこにヴィブラフォンがクールな味付けとして加わり、オリジナルなサウンドが形成される。このサイズでのドイツ公演は初めてというリーマン。企図したバンド・コンセプトは観客から熱狂をもって迎えられた。このバンド、日本でも観たいものだが、やはり経済面で難しいのかもしれない。
続いて登場したのはビル・フリゼール3。アイヴィン・カン(vln)+ルディ・ロイストン(ds)はまだアルバム・デビューしていない新ユニット。今回のメールスFがヨーロッパ初お目見えとなる。ビルにとってトリオは長く続けている基本的な編成だが、g+b+dsではなく、g+vln+dsは過去に例がなかった。他のヴァイオリン奏者とは異なるカンの個性。それは韓国系の出自と、ジャンルが混合して形成されたスタイルに基づく。胡弓を想起させる音色とメロディ・ラインを持つヴァイオリンを取り入れたバンド・サウンドこそが、90年代からしばしば共演してきたカンの、最大の起用理由ではないか。そして新世代黒人ロイストンの起用に関してもまた、ビルのこだわりが感じられる。前述のタイション・ソーリーと同じカテゴリーに属すテクニシャンは、本来繊細さと軽やかさに特徴があるビルのサウンドとはテイストが異なる。しかしビルはそのことをもちろんわかった上で、ロイストンをメンバーに引き入れたわけで、この点にも新トリオのサウンド・コンセプトが認められるのだ。
メールス・フェスティヴァル3日目
2010年05月23日
今日もメールスは快晴。午後1:00からプレステントでレセプション。メールス市長のスピーチを聞いた。昼の部のトップ・バッターはGrubenklang “Reloaded”。リーダーのドイツ人ゲオルグ・グレヴェは10年ほど前にリリースしたトリオのセロニアス・モンク集で、気になるピアニストに仕分けていた。今日のステージは1982年に結成されたオーケストラのリユニオンで、ルール地域が国際文化都市に選ばれた記念プロジェクトでもある。13人編成のオーケストラは、前列に7ホーンズ、後列にリズム・セクションという布陣で、ベースとドラムスが2名ずついるのが特徴。グレヴェはほとんど中央で指揮をとりながら、プログラムが進行。フル・サイズのビッグ・バンドには及ばない人数で、チューバ、ギター、クラリネット&バスクラリネット3名を盛り込んだ楽器編成により、オリジナル・サウンドを構築した。続いて登場したのはシュニーヴァイス&ローゼントロット。スイス、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツの欧州連合による女性ヴォーカル+p,b,dsの新世代クァルテットだ。このバンドのベーシストは1週間前に来日公演を行ったマグナス・ヨルト3のペーター・エルドで、その点でも興味をもってステージに接した。ヴォーカリスト=ルシアのスタイルは北欧的な囁き系で、シゼル・アンドレセンからの影響も認められる。鍵盤を使用して声を電気的に加工する手法も、北欧流だ。ヴォーカル抜きのトリオ・パートもたっぷりとあって、ピアノのフリー・スタイル・ソロや、かなり叩きまくるドラムスからは、ザ・バッド・プラスを想起させられた。3組目はペーター・ブロッツマン・シカゴ・テンテット。ドイツが生んだ最も著名なミュージシャンであるブロッツマンが、1997年にオクテットとしてシカゴで結成。その後テンテットを経て、現在は11人編成である。メンバーがステージに勢揃いすると、いきなり爆音の集団即興演奏が始まった。そこからブロッツマンが先頭を切り、その後各人のソロ・リレーで進行。中でもマッツ・グスタフソンとケン・ヴァンダーマークが楽器を持ち替えながら掛け合いを演じる場面が圧巻だった。ブロッツマンとヴァンダーマークのダブル・クラリネットはこの楽器をスイング/オールド・ジャズの領域から、現代にふさわしい生命力の溢れる武器へとその用途を転換させたのだと、改めて体感。ヨーロピアン=アメリカン・フリー・オールスターズと呼びたい圧巻のパフォーマンスは、昼の部のハイライトとなった。
夜の部が始まる前に、昨日メールスFに初出演したSuper Seaweed Sex Scandalの吉田野乃子に話を聞くことができた。以下にバ�